
いよいよ平成12年度がスタートしました。
新しい教育課程の実施を2年後に控えて、いよいよその具体的な動きが期待される年が始まった、という意味でこれまでの新年度の幕開けとは違った期待感に満ちたスタートになりました。お互いにがんばりましょう。よろしくお願いいたします。
それにつけても思うのは、「新しい学校づくり」「学校の再生」に向かう教育改革のベースにあるものは、なんと言っても「子どもの学びを保障する」ということでしょう。
学校の“学”は、文字通り「学ぶ」という意味ですが、それでは“校”にはどのような意味があるのでしょうか。
先日手にしたある本にヒントがありました。
| 「考える」という言葉を古くさかのぼると、罪人を刑罰に処するときに、
「…に勘ふ」と言いました。 ~中略~ もとの形「かむがへる」の「か」 とは、事とか所とかいうこと、「むがへる」の古形は「むかへる」で、 「向き合わせる」こと。犯罪者の実際にやった悪事が、刑罰の条文のどれにあたるかと事実と条文を突き合わせて決定すること、それが「かむがへる」でした。また、戸籍帳の記載と実際の田畑の配置を突き合わせて調べることも「校ふ」といいました。 大野晋 「日本語練習帳」岩波新書 p.7 |
すなわち、“校”とは「事柄を突き合わせて調べる」ことを言い表す言葉のようです。
そういえば、原稿が正しく印刷されているかどうか、印刷物と原稿を引き合わせて調べ、誤りがあれば修正することを「校正」と呼びますし、書物の文字や文章などの異同・正誤を調べて注釈をつけることを「校注(註)」と呼んでいます。
このように見てくると“校”という言葉は、「調べ」たり、そのことによって「考える」「判断する」ことを意味していると思われます。
すると「学校」とは、「学んで調べ、考えたり判断したりするところ」であり、決して「教えられて習う」ところではないことがわかります。
よくぞ「教習所」とか「伝習所」と名付けなかったものだと古人の知恵に驚かされるばかりです。教える側の論理が先に立てば、教え・伝える内容について学習者が習熟することが要求されるでしょうが、その論理を生かそうとすれば「伝習所(伝え習わせるところ)」とか「教習所(教え習わせるところ)」と名付けてもよさそうなものです。
しかし、古人はそうはせず、「学校」と名付けたのです。
いつの頃から「学校」という言い方がされるようになったのかは不明ですが、『孟子』に学校という言葉が見えることから、その時代にはもう「学校」という呼び方がされていたのだろうと思われます。
そのように教える側の論理ではなく、学ぶ側の論理と主体性を重視し「学校」と名付けた先人の知恵に今更ながら気づかさ驚かされます。
そのような学ぶ場としての「学校」がどうしたわけか、先人の思惑と異なり「伝習所」や「教習所」の傾向を強くしたのは、受験競争が激しくなった頃からだと思われます。
かつてユダヤ人のトケイヤーは、『日本には教育がない』(徳間書店)という本の中で
| 日本では子どもたちが常に「勉強」している。しかし、学校教育の中身は受け身になって「習う、教わる」(Learn)勉強だけで、主体性をもって、自ら積極的に「研究する、調べる」(Study)という意味の勉強は希薄である。そして、幼稚園から大学卒業までLearnするがStudyはまったくしない。 |
と指摘し揶揄しました。
「伝習所」や「教習所」からは、指示待ちの子どもや、他人に合わせてものを覚える子どもは育っても、自分から進んで創造的に思考するような子どもは育たないでしょう。
「生きる力」を育むことが重要視される背景として、自立の遅れや指示待ち人間からの脱却が強調されていますが、そのためには何よりもまず、Studyする子ども像への期待が大きいでしょう。
そのような子どもの育ちに貢献するためには、まず私たち自身が「正しい答え」や「正しい答えの出し方」を覚えさせることに血道をあげないことが大事なのではないでしょうか。
なぜなら、それを単に「覚えればよい」ということであれば、子どもたちは「調べ・考え・判断し決定する」という行為を放棄してもよいという意識を持ってしまうからです。
そこには自主的に考える必要がないからです。
私たちを取り巻く社会や自然などに存在する問題の多くについて、「答えははじめから分かっているわけではないのだ」という当然の認識に立って、誰かが知っていることを勉強するなどということは、誰も知らないことを分かることにくらべたら大したことではないということを子どもたちにわかってもらえれば、それぞれに発想や着想を豊かに働かせて取り組む余地が生じるでしょう。
自分の(自分たちの)知識は、自分の手でつくっていくのだ、そうしてよいのだ、という「学び」本来の姿に立ち戻ることができれば、主体的に「探り・調べ・考え・判断して」いけるような学習観の育ちが期待できます。
そのように子どもたちに働きかけること、それが学校の再生につながる一番の近道だと思われてなりませんが如何でしょうか。
私たちは、子どもたち一人ひとりが意欲的に学習や生活に取り組んでいけるようになることを願って日々子どもたちに接していると言って良いでしょう。
ことに学習への取り組みについては、積極的に前向きな姿勢で取り組めるような子どもに育って欲しいとさまざまに工夫を凝らしています。『意欲』とは、日常的な言葉で言えば、『やる気』のことだと言えますが、そのような『意欲(やる気)』にもいくつかの様相があるように思われます。
私は、大きく次の3種類に分類できるのではないかと考えています。
ア、状況こだわり型学習意欲
テストにこだわって試験勉強をしている場合、テストが終わってしまえば、
もう参考書など見たくもないと思うでしょう。この場合、テストという「状況」
にこだわって学んでいるので、このような学習意欲を「状況こだわり型」と名づ
けました。これは学習意欲が社会的な「条件」(例えば入試)や他者(親や友人、
教師など)との「関係」などに基盤をもつ場合を指しています。
「状況こだわり型」だけで学んでいる場合、学びはある目的(例えば「テスト
でよい点数をとる」「親を喜ばせる」など)のための手段となります。
従って、目的が達成されるともう学ぶ理由はなくなり、学びや考えがそれ以上
には深まってはいかないことが予想されます。
イ、内容こだわり型学習意欲
一方、知的好奇心に基づく自由な文脈では、書物や参考書などは自らの学びを
深める重要な情報源となるでしょう。
この場合、学びの「内容」(すなわち知りたいこと)にこだわって学んでいる
ので、この学習意欲を「内容こだわり型」と名づけました。
この内容こだわり型学習意欲によって取り組んでいる際には、その内容そのも
のについて深く学んでいくこと自体が学びの「目的」となります。
「もっと知りたい」「もっとわかりたい」「もっとできるようになりたい」といっ
た気持ちを支えに、さらにそれが膨らんでいくことが期待できます。
ウ、自己こだわり型学習意欲
さて、「こだわり」にはもう一つのタイプがあるでしょう。
たとえば「なんでもトップでなければ気が済まない」という人がたまにいます
が、このような人は、「トップでいる」という自己意識を保つために勉強に励ん
でいるのかも知れません。
自分という存在が優れていることを自分や他人に示すという動機から学ぶこと
や逆に自分が劣った存在であると他人から思われたり、自分自身でそう思うこと
が嫌で学ぶという学習の仕方もその範疇に入れて考えています。
このような場合、「自己意識」や「自己概念」にこだわって学びが起きている
と考えられますので、このような学習意欲を「自己こだわり型」と名付けました。
ざっと考えただけでも、このように『意欲(やる気)』をいくつかの様相に分けることができそうですが、私たちが子どもに望みたいそれはどのタイプのものかと言えば、アのタイプのものでないことは明白です。
なぜなら、ある状況から解放された途端、学ぶ意味が喪失してしまい、それ以上の「がんばり」や「努力」は無駄なものとしてしか意識できなくなってしまうことが予想されるからです。たとえ、そのときは進んでがんばっているように見えても。
そして、モノゴトの内容や自己の成長・拡大に「こだわる」からこそ、抜き差しならない課題としての『問い』が生じるし、次々に生まれる『問い』に応えるべく問い続けることが可能になると考えているし、そのことによって『学びの自立』への構えが無理なく身に付くだろうと考えているからです。
ところで、私たちは「意欲を持ちなさい」とか「やる気になりなさい」と言われたところで、内容や自己にこだわって積極的になれるとは思えません。
のっぴきならない、捨てては(放っては)おけない、すぐにでも取りかかってみたい、夢中になれる(なってしまう)、他のことは目に入らないと思えるような『おもしろい課題』でなければ、本来の意欲は生じ得ないでしょう。何の工夫もなく、「やる気になりなさい」と言うだけでは、意欲も生じないし学びも姿勢も育たないのです。
かつては、「教え方がうまい」という言葉に象徴されるように、先生一人ひとりが指導技術を高め、そのテクニックで「意欲を引き出し」「わかりやすく」指導する授業が評価され求められました。その結果、そのときはわかったような気になるけれども後になって考えてみたらよく理解できていなかった、ということもよく見受けられました。
大事なのは、「教え方」よりも子どもに「その気になってもらえるような工夫」ですが、授業を離れたときでも問いが持続しこだわりを捨てきれないような「内容のある課題」を準備できるかどうかがこれからの学習を構想する上での正念場だと言えるでしょう。
それは、学習指導とは「教えること」ではなく「学びを指導すること」である、というとらえに立てば自明のことであると言えます。
私たち自身が「やる気になる」「その気になる」のは容易ですが、子どもに「やる気になってもらう」のはずっと難しいとも言えますが、そのような学習を構想し提起することは単に「やる気」だけの問題ではなく、自己実現に向けて自分を切り拓いていくもっとも大切な構えの育ちにつながるはずだと私は考えています。
徒にテクニックに走ることなく、目の前にいる子どもたちがつい手を出したくなってしまうような学びが期待できる内容に組み替えていく、他にない『創意と工夫』をしていきたいものです。『意欲』は、持たされたり引き出されたりするものではなく、もともと子ども(人間すべて)がその内に持っているものだと思われるからです。
先日、散歩の折に立ち寄った本屋さんでおもしろい本を見つけましたので、今回はそれをご紹介することにします。
本のタイトルは『何とかしなくちゃ今の教育』(ライフ企画、1,340円)です。
今、教育は社会の中で最大の関心事の一つですが、この本はライフ企画という出版社が一般から教育に関する短文を募集し、その中から連城三紀彦氏(作家)や田中節夫氏(椙山女学園大教授)など4人の審査員が選び出した優れた作品を掲載する、という形で出版されたものです。
子どもから大人まで総数4074通と多くの応募があったようですが、なるほどと頷かされるものから、ほっとさせられるもの、思わず「本当のことなの?」と驚かされるものまで、さまざまな教育への感想やら意見やらが載せられています。
その中からいくつかご紹介しましょう。
**********************************************************************************
おぼえる事がいっぱいで、
ぼくの頭がはれつしちゃうよ。
こんなにべんきょうしないと大人になれないの?
高井俊宏(小学2年生)
*********************************************************************************
不思議や疑問はいっぱいあった。
でも、いつのまにか感じなくなってた。
だって、覚えるだけでいい点とれたから。
木戸小百合(学生 22歳)
*********************************************************************************
『無限の可能性』って何だ。
ピアノ、サッカー、体操、学習塾・・・早期教育って可能性を
ひとつひとつ消していくことだろうか。
上野洋子(主婦 38歳)
*********************************************************************************
得体の知れない偏差値にカリカリするお母さん。
「五体満足でさえあれば」と願い、生まれてきたその子を抱いた
時の喜びを忘れたのですか?
子供の笑顔こそが、最高の宝ではなかったのですか?
秋田圭介(自営業 50歳)
*********************************************************************************
「教育」は「幸福」になるための道具のひとつであって、
それで「不幸」になるくらいなら、ない方がましでしょう。
野田裕子(会社員 36歳)
*********************************************************************************
年をとって初めて字を習った方がこんなことを言っています。
「夕日という字が書けるようになって、初めて夕日を心から美しいと思った」
このように教育は生きる喜びです。子供たちには、好奇心を持ち、
学ぶことの楽しさを感じてもらいたい。
K・O 女性(会社員 26歳)
**********************************************************************************
小学校5年生の時の国語の先生、お元気ですか?先生は、みんなの意見を聞いた後
おっしゃいました。「全員正解です。人間はそれぞれ違っているんだから、
考えたり、思ったりすることも違ってあたりまえ。だからみんな正解です」と。
国語のテストもいつも感想や意見を書くところがたくさんあって、
みんなマルでした。
大澗和子(38歳)
*********************************************************************************
小学6年の時の算数のテスト。
裏面に漫画を描き、白紙で出した。翌日テストが返され、見ると
「『マンガ百点』次はマンガと同じくらいガンバレ」と赤ペンで書いてあった。
うれしかった。
それ以来、勉強しようと心に誓った。
阿部広海(地方公務員38歳)
**********************************************************************************
短い文章の中に、教育に対する思いや願いが見事に言い表されていて、そのエッセンスが浮き彫りにされているとは思いませんか?
すこぶる示唆に富んだものが数多く掲載されていて、紹介し尽くすことはできませんが、最後にもう1点だけご紹介します。
*********************************************************************************
昔、私が試験で赤点だった時。ある先生が「問題をやらなかったのか?
それとも解らなかったのか?」と聞いたので、私は「解らなかった」と
答えた。
すると、「解らないのは、私の教え方が悪かった」と謝ったのには驚き、私は次回の
試験からは、絶対頑張ろうと思った。
原田つとむ(フリープランナー 48歳)
**********************************************************************************
子どもたちの、そして人々の素朴な教育に対する疑問や期待に応えられるように、そして教育のあるべき姿の実現に向けて、率直に真摯にこのような声と向き合うことも大切なのではないでしょうか。
何としたことでしょう。一昨日、私の次女のノートパソコンが故障してしまいました。 娘が言うには、特に何か間違った操作をした訳でも、故障につながるような過ちをしたつもりもないのに、電源スイッチを入れても何も表示されなくなったと言うのです。
電源ランプが点いているところをみると、電源部分の故障ではなく、ハードディスクにアクセスしている様子がうかがえないところから推察するに、どうやらハードディスクを読みに行くまでの間に何か不具合(それもかなり決定的な)が生じてしまったとしか思えないような故障なのです。急いで、それを買った土浦の量販店に修理を頼みに行ったのですが、悪くするとハードディスクそのものを交換することも覚悟してくださいとのこと。
いっそう悪いことに、娘はこれまでに書いた論文やレポートのたぐい、あるいは友達とやりとりしたメールやそのアドレスなどのバックアップをまったく取っていない、というのです。娘が言うのに、「つくづくコンピュータは便利だけどこわい。」
本当にそうですね。先生方の中にも、何度もそういう経験をされて「後悔する前のバックアップ」の実行を心がけておられる先生もいらっしゃるのではないでしょうか。
ところで、とても便利な道具(ToolあるいはInstrument)であるはずのコンピュータですが、道具とは言いながら私たちの身の回りの他の道具とはずいぶんその性質が異なるのではないかというのが、私の実感です。と言うのも、他の道具でこれほどマニュアルが必要なものはないだろうと思われるからです。使いこなせるようになる迄にさまざまな労苦を使用者に強いる、というのが電子の道具の特徴だと言ってしまえばそれまでですが、それでは本当の『道具』とは言えないのではないか、と私は常々考えています。
同じ『道具』でもノコギリを買ってきたとして、マニュアルはついてくるでしょうか。 また、音楽を演奏するための道具(Musical
Instrument)であるピアノを買ったとして、マニュアルを読み漁る必要があるでしょうか。
本来の道具は、それを手にした時から即座に使いこなせるものでなくてはならないはずです。もちろん、思い通りに『使いこなす』には、それなりの習熟が必要であるとしても、まがりなりにも『使える』状態で売られていて、買ってくれば何の準備もなくある程度は『使える』というのでなければ、本来の『道具』とは言えないはずです。
ところが、コンピュータ(ワープロ専用機でも)は、何かしようとすれば、そのための手続きを知らなければなりません。それがアプリケーションごとにあることから、コンピュータのマニュアルだけでなくさまざまなソフトの使い方、操作法を教えてくれる参考書のたぐいがたくさん出版されていて、書店の本棚にたくさん並べられています。
どうやら、コンピュータをつくるメーカーやソフトをつくるメーカーの人たちは、使う前に『覚える』ことがたくさんあるのは当然だ、と思っているようで、あれもできます、これもできますと売り言葉を並べる割に、それは決して容易なことではなく、それをするには多く努力を使用者に強いているということを知らない(あるいは気づかないふりをしてきた)ように思われます。
これまで、ある商品を使う人(購買者)は、それをつくって売る人(メーカー)の下位にあって、使いこなせないのは自分の知識が不足しているから、あるいは技術が不十分であるからに違いないと思いこまされてきたようにも思われます。
マニュアルというのは、その道具に触れただけではわからないことを補足説明する、いわば注釈書です。注釈書が分厚い、ということは補うための説明が多すぎて、その道具は道具として十分ではなく、道具としてのできが良くないということなのだと使用者が『わかり直す』ことや「なぜこんなにわかりにくいのだ?」と不平を述べても良いのであって、それこそが道具を本来の『道具』にしていく最短の道ではないか、と私は考えています。
ですから、使用者はメーカーに遠慮せずにどんどん注文をつけるべきなのです。
だって道具が主役なのではなく、使う人こそが主役なのですから。
それに、コンピュータは成長が固定してしまった道具ではなく、いわばどこまで行っても発展途上の、成長し続けることが予想される『新しくなり続ける』成長過程の道具だと思われるからです。
もうメーカーの言いなりになるのはやめて、私たちの欲しいのは「このような道具だ」と主張する「道具の主人」になることが必要でしょう。
情報リテラシーの教育の必要性が叫ばれていますが、それはコンピュータに使われ振り回される人間を育てることではなく、コンピュータをまさに自分の情報操作や表現の道具として『使いこなす』人間を育てることです。コンピュータを使えるかどうかではなく、情報を操作し扱えるかどうかの方が重要で、コンピュータがあった方が「より確かで早く」それが「便利」だから使うのだ、というふうにとらえてコンピュータをもっと扱いやすい道具にし、使役していくべきなのです。
小さい頃からコンピュータに慣れさせ、コンピュータを使いこなせる人間に育てる、ということがまことしやかに言われて学校現場にたくさんのコンピュータが導入されましたが、コンピュータは先にも言ったように今の姿、今のシステムのままでとどまるとは思えません。それに小さい頃からコンピュータに触れていなければ「コンピュータ・アレルギー」を起こして、大きくなってもコンピュータを使いこなせるようにならないのではないか、という心配もただの杞憂でしかないだろうというのが私の感想です。
だって、私たちが小さい頃はコンピュータなどは存在しませんでしたし、そんなものが出現するなどということも考えていませんでしたが、大人になってから出会った道具であっても結構(それなりに)使いこなせているではありませんか。
大切なことは、新しいものに出会ったときにそれに隷属するか主人公となるかの違いだとも言えますが、子どもが便利な道具、日常的な道具として使うものであることを考えると、使う前の準備として覚えなければならないことが多い、というのは決して良いことであるとは思えません。コンピュータを身近な道具として「使えるもの」にしてくのは、私たち使用者、利用者の要求にメーカーのテクノロジーがどれだけ応えられるか、ではないかとつくづく思うのですがいかがでしょうか。
楽しいはずのゴールデン・ウィークの真っ只中に、何とも言えない暗澹たる気持ちにさせられる事件が起きてしまいました。17歳の少年が、西鉄の高速バスを乗っ取って占拠し、しかも殺人まで犯してしまうという心が凍り付くような事件です。
幼い小学1年生の女の子に、刃渡り40cmの包丁をつきつけ、人質にするという考えられないような状況が長時間にわたってリアルタイムで報道され、全国の目が中国自動車道に釘付けにされてしまいました。
その数日前には、愛知県でやはり17歳の少年が『人を殺す経験がしたかった』というただそれだけの理由で見ず知らずの女性の命を奪う、という事件が起こったばかりでした。 しかも彼は、若い人には将来があるのでまずいと思ったので、お年寄りをねらったと言います。また後日の取り調べの中では『死んでしまった人に謝っても意味がない』とも洩らしているとか。身勝手というか常識では考えられない理屈をもって人の命を絶ってしまうというその行為と行為に陰に何があったのか見いだせずに社会全体がとまどいを隠せないようです。
今の子どもたちに何が起きているのか、何が彼らをそうした理不尽な行動に走らせるのか、テレビのニュース番組でも多くのコメンテーターがその背景を探ろうとさまざまな発言をしています。
あるニュース番組では、中高校生を対象としたアンケート調査に基づいて、キャスターが「今の少年たちは、何か悩みがあったときに相談できる相手がいない。親はもとより、先生にも相談したくないと思っている。また、友達もおもしろおかしく遊ぶ仲間ではあっても、深刻な問題を語り合える相手とは思っていない」のだと言っていました。
そして、そういった相談相手のいないことが自分を見失わせる大きな理由になっているのだろうとコメントしていましたが、それはどうでしょうか。
まるで、人間は『誰かに支えてもらう』ということがなければ、しっかりと立って歩けないとでもいうように聞こえます。
相談相手がいないから、一緒に語り合う深い絆で結ばれた仲間がいないから、さしたる理由もなく誰かを傷つけ傷つけることで自分を見いだすのだ、というのは人間を元来「一人立ちできない弱い存在」として見る見方でしょう。
そうではなく、多少の困難があってもくじけずに、他に頼らずに自分の足で立って歩けるのだ、自立せよと少年たちに促すのが社会と大人の役目ではないのでしょうか。
たとえ一人になろうとも、勇気を奮い起こして生きていけるという構えを育てる事の方がよほど大切なことで、頼るべき相手を持つことが大事だとするそのキャスターの発言には疑問を抱かざるを得ません。なぜなら、相談できる相手がいないから、心が不安定になり、そのような危うい行動をしてしまうのだ、と言っているのですから・・・。
私たちは、子どもたちに何より自立をこそ促さなければならないはずですが、それは決して孤立を意味してはいません。
仲間に手をさしのべることも、仲間を理解することも、共感することもできるが、一方的に依存する甘えを拒否して独立独歩の精神で人生を生きていけるのだ、そうしようよと社会全体で促し励ましてやるべきなのです。
それはさておき、このところ困ったものだと思うのは、このような事件が起きるたびに、心理学を背景にしたコメントがあちこちで聞かれ、さもわかったかのような意見を述べる人たちがいること、そのような情報が溢れていることです。
科学的な研究を土台にした平均値と法則からなる一般化され通俗化された『子ども学的諸知識』が、目の前にいる子どもを理解し、その子と関係を結ぼうとするとき、どれほどの目を遮り弊害をもたらしてきたかは、この十数年の経緯をみれば明白です。
子どもたちは、大人の安易な思いこみによる『理解』を否定し、「まるでわかってない」とますます大人との距離をつくって自分の世界、自分の論理に逃げ込み、「子どもが見えなくなった」「彼らの心がわからない」と大人をして嘆かせるようになってしまったのではないかと思われるからです。
この十数年間、目の前にいる『生きた子ども』をわかろうとせずに、マスメディアを通じて流される子ども理解のバイブルやマニュアルに頼って、画一化された説明に安住し、自分の心でわかろうとすることを放棄してきた結果、そうなってしまったのだということに私たちは気づくべきなのかも知れません。
残りの行数が少なくなってしまいました。心理学者の河合隼雄氏の次の言葉をご紹介して終わりにします。
| 臨床心理学などということを専門にしていると、他人の心がすぐわかるのではないか、とよく言われる。私に会うとすぐに心の中のことをみすかされそうで怖い、とまで言う人もある。確かに私は臨床心理学の専門家であるし、人の心ということを相手にして生きてきた人間である。しかし、実のところは、一般の予想とは反対に、私は人の心などわかるはずがないと思っているのである。この点をもっと強調したいときは、一般の人は人の心がすぐわかると思っておられるが、人の心がいかにわからないかということを、確信をもって知っているところが、専門家の特徴である、などと言ったりする。一般の人は、ちょっと他人の顔つきを見るだけで、「悪い人」とか「やさしそうな人」とわかったように思う。これに対して、専門家はどれほどやさしそうに見える人でも、ひょっとすると恐ろしいところがあるかも知れない、と思う。あるいは、怖い顔つきの人に会っても、あんがいやさしい人かも知れない、と思っている。要するに、簡単に判断を下さず、人の心というものはどんな動きをするのか、わかるはずがないという態度で他人に接しているのである。 「こころの処方箋」 新潮社 1992.pp.8..9 |
個性を生かす教育や主体的な学習活動を展開していく上で、ますます重要になってきたのは、子どもを理解することだと言ってよいでしょう。「子どもがわからない」というのでは、生かすべき個性もわからないし、子どもの主体性を伸ばすこともできないと考えられるからです。それはまた、子どもの学校生活の土台となる学級の経営の出発点であるとも言えますが・・・。
そのことに関して、児島邦宏先生(東京学芸大教授)は
~中 略~
当然のことではあるが、子どもの内面世界をどこまで把握できるかである。
つまり「内面理解」に関してである。
気になるのは、「忘れ物が多い」「消極的である」といった具合に、
学級経営案や指導案の記述が、「観察」レベルの表面的な理解にとどまって
いる点である。
これでは、親と同じで、教育の専門家とはいえない。
観察の先に何がみえるかである。
まず、「なぜ忘れ物が多いのか」という「解釈」が必要である。
「としたら、このままでよいのか、何らかの手だてが必要なのか」という
「教育的判断、診断」が続く。
さらに、「何らかの手だてが必要とすれば、どんな手だてをとればよいの
か」という「処遇、手だて」が考慮されなければならない。
こうした観察一解釈→診断一処遇という読みの深さこそ、一人一人を生かす
方途となる。
『子どもの未来をひらく学校』教育出版
1996 pp..45..49
と指摘しています。
子どもを「理解する」ということは、子どもをどう「評価するか」ということと密接な関連がありますが、私はそれを思うとき、病院のお医者さんを連想します。
病院のお医者さんは、私たちの病気を「診断」してくれ、その治癒のために適切な治療を施してくれます。インフォームド・コンセントなどということが言われる前から、この病気の原因はこれこれであり、それを治したり再発を防いだりするためにはかくかくの治療が必要だ。私もがんばるから患者であるあなたも一緒にがんばりましょう、と治療の方針(目的や手段)を示して、そのめやすまでも示してくれます。
決して「あなたの体の悪いところは、大腸です。治すように努力しなさい。」と診断だけ下して済ましてしまうことはありません。
翻って学校での私たちの活動は、いかがでしょうか。
児島先生の表現を借りれば『「忘れ物が多い」「消極的である」と観察レベルの表面的な理解をすること』で自分の「診断(評価)」は済んだと安心してしまうことはなかったでしょうか。それだけでは本来の「診断」と呼べる「子ども理解」にはならないということはお医者さんの例をみれば明白です。、子どもの成長を保障することを何より重視する学校においては、本来の「診断」の姿に立ち返ることこそ必要でしょう。
つまり、「観察」から得られた現実の姿から、その原因と処方を探り出し、子ども自身にもそのことをK・R情報として伝え、その子がその処方を受け入れ自分から治療に向かおうとする意欲が持てるようにすること、それが「診断」の本来の意味であるし、そうできることが「専門職」としての私たちに求められていることだと言えるでしょう。
それが本来の「診断」としての「教育的判断」だと言えますが、それは「治す」ことを目的とした治療という意味ばかりでなく、「よりよく成長していく」ための処方という面でも(いやそちらの方がより重要な意味を持つものとして)意識されるべきだろうと思っています。
その中ではもちろん先生が「そうしなさい」と子どもをして治療に向かわせるのではなく、子ども自身もそうしたいと思え、先生と子どもとが手をとって治療に取り組む中で、子ども自身が「自分の力で治そう(伸ばそう)」とするからこそ「個性を発揮する」あるいは「個性を生かす」ことにつながるだろうと私は考えています。
子どもたちを見る(診る、看る、観る)ということは、私たちがそれぞれに持っているある価値観を基に見て理解していると言えますが、そのフィルターが妥当なものであるかどうかについての配慮も大切かも知れません。
『落ち着きのないうるさい子』と見られていた子が、『活発で元気に溢れた行動的な子』と評価してくれる先生に受け持たれたとたん、生活のあらゆる場面で生き生きと行動できるようになったという話はよく聞かれます。
ある価値基準にしばられた目では見えない価値(よさ)が他にもたくさんあるし、そのよさをもっと伸ばせる手だては何か、と考えたり探ったりする心はもちろんのこと、多様な価値観(モノサシ)があるかも知れない、あるに違いないと一歩下がってゆったりと見ようとする構えが大切なのかも知れません。
何よりも子どもが自分のよさや持ち味を十分に発揮してさらに伸ばしていけるようにしてやることが私たちの務めだと言えますが、そのためには子ども自身が「よい自己概念」をもって生活していけるように見守ってやること、一緒に歩き出すことが大切なのではないでしょうか。
生まれたときから、親や教師から「あそこが悪い、ここが悪い」と言われ続けた子どもは、「こんなつらい世の中、生まれてこなければよかった」「自分はダメ人間だ」と、思い込まされてしまうでしょう。そうではなく「この世に生まれてきてよかった」と、自己有用感、自尊感情をもち、自信と誇りをもって生きていけるように支援することこそ、「生き方」の教育の出発点だと思われるからです。
病院のお医者さんの患者に対する応対からそのようなことを思い起こして、これまでの自分の姿を振り返った次第です。
問いの解決に向けて取り組む中で、もっとも大切なことは何かと言えば、「途中でへこたれず、ねばり強くやり遂げよう」とする姿勢なのではないか
と私は考えています。そのような姿で取り組んでもらえるような授業をしてみたいものだと思いながら、なかなかそんな授業を仕組むことができず、
ついつい「もっとがんばりなさい」と意味のない励ましをしてしまう経験を積み重ねながら30年経ってしまいました。
子どもが自分の達成の成果について「こんなところでいいや」「この程度で十分」などと妥協してしまわずに、「もっとこうしてみたい」「よりよい方法
はないか」とより価値の高い方向へ進んでいくことができれば、自己学習力を発揮している姿と呼んでよさそうです。
波多野誼余夫獨協大教授は、「自己学習能力」について次のように指摘しています。
「自己学習能力」
1、自己の理解の程度を識別し、かつそれを深めるのに適切な方略を
採用する「自己制御能力(モニタリングの能力)」
2、これを支える「深く知ろうとする意欲」
3、「自分の知的可能性についての自信」
岩波新書 『知力と学力』PP.123
波多野誼余夫・稲垣佳世子
無我夢中で我を忘れ、時間を忘れてものごとに熱中してしまう、いわば「フローの状態」でやり遂げようとすることは私たちにもよくあることですが、
そのようなときに私たちの内には、ついつい自分の達成状況を監視して「○○のようにできればよいだろう」という「めやす」が生まれ、それに照らし
合わせて適切な手段をとったりその実現に向けて苦心したりしようとする姿勢が生じるようです。
つまりそのような状況の中では、自己内自己が自己を客観的に見つめ、自己を評価する、つまり「メタ認知」が働くようなのです。
ところで、学校での学習の中では、そのような「めやす」を学習者自身が持って自分の学習活動をコントロールし、自ら学習の成果をめざすということ
については、さほど重視されてきませんでした。
日常の生活の中で我が子に接するときには常に「めやす」を意識しているのに・・・。 たとえば、幼い子どもをお風呂に入れているときに、多くの親
は『よく体が温まるように、肩までお湯につかって100数えてみようね。』などと言うはずです。
ここでの「めあて」は、「体を温めること」であり、「めやす」は「100数える間の時間」です。多くの親は、その程度の時間、お湯にゆっくり浸っていれば湯冷めしないような体の温まり方ができるだろうと思っているからそうするのでしょう。
また自動車学校では、右折や左折、縦列駐車や坂道発進など、運転の経験の浅い生徒に対してとてもわかりやすい「めやす」を示して指導してくれます。
アクセルをふかしエンジンの音がこのように変わったときにサイドブレーキをはずせば、うまく坂道で発進できるとか、運転席から見てボンネットの一番前のラインが道路の向こう側の線にかかったときにハンドルをきれば、脱輪せずに曲がれるといった具合です。
「(逆戻りせずに)発進」したり「(脱輪せずに)曲がる」ことが「めあて」で、「エンジンの音が変わ」ったり「(道路の線に)合」ったりすることが「めやす」であることはもうおわかりでしょう。
私は、教室の子どもたちが持つべきは「めあて」だけではなく「めやす」も併せて持つべきだと長いこと考えてきました。
しかし、上に挙げた2つの例は、学習者が「めやす」の達成に向けてがんばれることはあっても、それがどのような意味を持つか、ということについて学習者自身が意識できていない、という意味であまり良い例ではないな、とこの頃考えています。
自己評価できるためには、「めやす」の持つなかみが学習者自身に「大切なもの」として意識され、常にその観点に立ち返りそこから自分の活動を見直し確かめ、よりよい方向へ進むべく制御(コントロール)していくことが欠かせません。そのためには、「めやす」が指導者から与えられるものではなく、学習者自身の内に自ずと生じてくるようなものである必要があると考えるからです。そこで「めあて」そのものを工夫し、「めあて」が提示された瞬間に学習者が『こんなふうにしてみたい』とか『こうできればいいんだな』というように「めやす」が持てるような「めあて」にしたいと思うのです。
こんな例を挙げればわかっていただけるでしょうか。
季節はずれの話題で恐縮ですが、この頃はバレンタインデーに手作りのチョコレートを贈ることが流行っているとか。そこで、仮に「大好きな人に喜んでもらえるようなおいしい手作りのチョコレートを作って贈ろう」という「めあて」を設定したとしましょう。
そうすると、私たちの内に、まず相手に喜んでもらえるようなチョコレートにするために、どんなデザインにするか、どんな味にするかなどについて工夫の観点が生じることでしょう。チョコレートを作るための材料は何?どうしたら作れるの?どんなことに気をつければおいしくなるの?といった疑問を解決するための探索活動も自らの手で展開していけるでしょう。
しかも、作りながら「相手においしいと言ってもらえるようなデザインや味」を求めて、見直しや確かめの活動をついついしてしまうことが予想されます。舌触りのなめらかさはこの程度でどうだろうか、苦さと甘さのバランスはこれでいいだろうか、硬さ(柔らかさ)はどうだろうか、といったことについて自分の満足のみならず、相手の立場に立ってまさに「問い返され」ながら活動を深めていくことができるでしょう。
そして、そこでは「作って贈る」という「めあて」と「おいしいと喜んでもらえるような」ものに迫る「めやす」とが不離密接な意味あるものとして、作り手に意識され作成中ずっと「問い続けられる」環境として働くことが期待できます。
そのような学習環境としての「めやす」が無理なく生じ、子どもたちに意識できるような「めあて」の設定を工夫することが主体的な学習を生み出す一番の近道、自律的な学習の姿に近づく最大の要因だと思われてなりません。
いまどこの学校でも「インターネットを利用した教育実践」が数多くなされています。 そして、その学習の多くが、いわゆる「調べ学習」という形でなされています。
ところで「調べ学習」というのは、どういう「学習」なのでしょうか。総合的な学習に限らず、各地でそして各教科で「調べ学習」と呼ばれる学習形態が実践されていますが、その中では、まず子どもたちが「これこれについて調べる」という課題を持ちます(自分できめる場合も、先生から与えられる場合もありますが)。そのあと、図書館(図書室)やインターネットを活用するなどして情報収集し、それらを「ノートにまとめる」という手順で行われます。
私が垣間見たところでは、確かに書籍やデータ・ベースの中を探索して情報を収集し、調べているように思われるのですが、『ここにこんなことが書いてあった』『これはこんな意味です』とそれらに書かれていることをノートに写しまとめるだけで『わかった』と充足してしまうことが「学習」と呼べるのだろうか、という感想から逃れ得ません。
どこかに書いてあることを「写し取り」「まとめて」「発表する」ということが「調べて学習する」ことのなかみで、そこに「感想」でもつけば二重マルがもらえるというのが「調べ学習」のようなのです。
どうしてこれが「学習」になるのかはわかりませんが、ともかく、こういうことを「調べ学習」と呼んでいるようです。
もう既に世の中では周知のことがらをなぞって「覚える」ことをねらうのであればともかく、「調べ・探索し、発見し検証して知を構築する」ことを体験的に学ぶ、つまり学ぶことを通して学び方を身につけることをねらうのであれば、このような「調べ学習」と呼ばれる学習に意味があるとはどうしても思えません。
佐伯胖東大教授も、そのことに関して次のように指摘しています。
******************************************************************************
もちろん、子どもたちが自主的に課題意識をもち、議論を深めた上で、「どう
してもここが知りたい」ということで調べ、その結果をさらに批判的に検討する
という、まさに「探究活動」となっているケースもなくはない。
たとえば「オクマジャクシの成長」の観察の中でそのエサを多種多様に実験して、
「野菜」よりもにぼしやウインナーなど肉類の切れはしを好むことをつきとめた
り、「シッポ」がなくなる謎の解明を進めていくうちに現代生物学の最先端での
最近の「発見」を知るに至ったりという実践がある。
しかし多くの場合は、子どもたちには「仮説」もないし、したがって「検証」
もない。自分なりの疑問も発見もない。対立する意見の交換も議論もない。
ただクイズ番組でのクイズヘの「解答」を求めるように、「これこれについて
はどうなっていますか」と問い、「こうなっています」という答えをみつけれ
ばそれでオシマイという断片的知識の収集だけである。誰かが「ここがおかし
い」といっても、「でも、調べたらこう書いてありました」といえばそれで済
んでしまうことが多い。
「日本各地の伝統工芸を調べました」「日本各地のお雑煮の中味を調べました」
というような報告は、それ自体「おもしろい」にはちがいないが、「だから、
どういうことが言えるのか」がまったく追求されていない。
佐伯胖 「新・教育とコンピュータ」岩波書店 1998
****************************************************************************
さまざまな情報を収集し、フィルターにかけて選別したり、一見関係がなさそうに見えるいくつかの情報の間に新しい関係を見いだしたり、それをもとに今まで自分が持っていた知識を組み替えたりすること、それが本来の「調べ学習」の意味であるはずです。
その意味では、先に述べたような学習は「学習」ではない、つまり「お勉強」の域を出るものではなく、それが「自律的な学習」の実現に役立つものであるとはとうてい思えませんし、ひいては「学習の自立」につながる「学力の育ち」に貢献できるものとも思えません。
自分なりの納得を伴って「わかる」ということは、決して借り物の「誰かがそう言った(あるいはそう書いた)」ことからお手軽に得られるものではなく、「だからどうなのだ」「なぜそう言えるのだ」「それは他の問題でも言えることか」「そう言えるとして、自分はどうすればよいのか」などという検証や自分への問いかけを経てこそ得られるものなのです。そのような過程を経てこそ、『あゝ、やっぱりそうか』とか『なるほどそうか』と腑に落ちて「わかる」はずなのです。
私にはインターネットを活用しようが図書室の書籍を活用しようが、従来行われてきた「調べ学習」では学習対象の内容について「知る・わかる」ということよりも、『ここにこんな情報があった』という情報の所在について知ることしかできないのではないかと思われてなりません。それは、知りたいことがあったときに、どこを調べればよいか、何を手がかりに調べればよいか、という方法を知るにはひょっとすると有効かも知れませんが、子どもにとって(あるいは大人にとってもそうかも知れませんが)内容に迫る働きかけの中でこそ、本来の学び方、つまり「探索の仕方・収集の仕方・選択の仕方・組み立て方・組み替え方・関係を見いだす見方や考え方・まとめ方等」などが自分にとってどうしても欲しい力や構えとして身につけていくことができるはずです。
そうした働きかけが子どもの主体的な動きとして出てくるためには、子どもが喉から手が出るほどに手に入れたい、解決したいと思えるような「問い」が生じると期待できそうな課題が提供されること、あるいは日常の環境の中にさりげなく設定されていることなどが大事なのではないでしょうか。
そしてもっと言えば、情報は容易に手に入っても、それだけで学習は終わりではないし、そこから先が実は本当の学習なのだ、ということを子どもたちにわかってもらう必要があると私は考えています。どうしたら、自分にとってかけがえのない知識となり、血や肉となる知識となるか、そしてテストが済んだら忘れてしまうような行きずりの知識ではなく、生きて働く知識になるのかということについて実感を伴ってわかってもらえるように働きかけたいと思うのですが、いかがでしょうか。
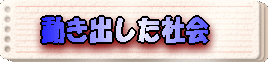
9月も半ばを過ぎ、運動会も終わった今頃、ちょっと旧い話で恐縮です。
夏休み期間中に研修センターで教頭研修講座が行われました。
県内すべての小中学校の教頭をA・B2つのグループに分け、2日間にわたって行われた研修講座でしたが、その中でおもしろい講演をお聴きすることができましたので、今回はそれをご紹介することから始めたいと思います。
当日の日程をざっとご紹介すると、
9:30~ 講義「本県の学校教育について」 教育庁義務教育課副参事 梅原先生
〃 課長補佐 川村先生
10:10~ 講義「教育課程と総合的な学習の時間」 日体大教授
中野 重人先生
12:40~ 講話「社内における組織管理と店所の自律的経営の強化について」
東電茨城支店長
山口 学さん
14:00~ 講義「新しい学校づくりと教頭の責務」推進協議会長
海野 千秀先生
というものでした。
お気づきかと思いますが、異色な「東電支店長」がここに名を連ねています。そして、その講話がすこぶる興味深いものだったので、ご紹介しようと思うのです。
私は知らなかったのですが、先生方はご存知だったでしょうか。
茨城県内で使われる電力はすべて「自動的に」東京電力から買っているものとばかり思っていたのですが、平成に入ってから方針の大転換が行われ、どこの電力会社から電気を購入してもよいということになっているのだそうです。東北電力からでも中部電力からでも、あるいは新規に電力事業に参加している一般企業による電力会社からでもよいのだそうです。もっとも一般家庭のように消費電力の小さな購入者はその対象からは除外されていて、工場などのように大量に電気を使用するところに限られるようですが・・。
そこで、それぞれの電力会社は競争に耐えられるような経営姿勢の確保に積極的に取り組み、組織の大改革を実行し、その成果を挙げているのだというのです。
従来は、まず電力を生産するコストをベースに、それに会社の利益分としての金額を加算し、そこから料金を設定して販売するというあたりまえの価格設定をしていたそうです。
ところが、それは購入者に満足のいく価格設定ではないし、ひいては売り上げの伸びにもつながりにくいということで、現在は、まず売れる価格を想定し、そこから利益分を差し引き、コストを設定し、そのコストで生産できるような体制づくりをしているのだ、というのです。
つまり供給者サイドの経営からお客様本位の経営の転換をするために、経営資源を最大限に活用した高効率の生産体制づくり、組織替えを実行したのだそうです。
そのためには、ずいぶんと思い切ったこと、いたみを伴うことも断行したようです。
例えば、これまでは現場の担当者の上に副主任、その上に主任、さらにその上に副課長、またその上に課長、部長補佐、部長と役職が名を連ね、担当者が現場の注文に応じて何かしようとすれば副主任から部長まで順を追って承認印をもらって歩かなければならず、一つの仕事をするのに時間がかかることがしばしばだったようです。
それでは顧客へのスムーズなサービスができにくい、顧客離れが起きてしまう、あるいは人件費もかさむ、ついにはコストがはねあがって顧客離れに拍車をかける、といったことから組織を組み替え、人員削減をしたと言います。
具体的には、全体の職員をいくつかのグループに分け、グループの構成員はダイレクトに部長と連絡が取れるような組織にしたのだそうです。これでずいぶんと作業がスムーズに効率よく行えるようになったと支店長。
それにしても、それまでは主任だ課長だと言っていた人も従来の部下と同じ立場のグループの一員になってしまうわけですから、組織内でずいぶんと抵抗もあったに違いありません。
しかし、思い切ってそれを断行した根っこにあって強い推進力となったのは、「お客様本位の経営への転換」の理念だったようです。
そう言えば、以前に聞いた話ですが、アメリカのサウスアメリカン航空は、倒産や人員整理に追い込まれる会社の多い航空業界にあって、驚異の業績を上げているというのです。そして、その成功の原因は、この東電と同様に「顧客のニーズに応えること(顧客満足度を図ること)」に徹底的に取り組んだことによるのだそうです。
その徹底ぶりによって、他の航空会社よりもずっと低料金で(何と3割、4割などというものではなく、半額以下の路線もあるのです)お客を運び、しかも旅客からの苦情件数も他の航空会社よりずっと少ないというのです。(苦情のフォローも旅客の立場に立って、
さまざまに工夫されているようです。)
どうやら今、社会を再建するキーワードは「顧客のニーズ応え、顧客満足度を図り高めること」であるようですが、それは学校でも大いに参考になるし参考にして欲しい、と考えたからこそ研修講座の講義に組み込まれたのでしょう。
学ぶ当事者である子どもたちが「学ぶことを喜び、満足を得る」ことができることよりも「教える側の論理」を強調してきた在り方を見直し、新しい視点で学習を、そして学校をつくりかえていくために私たちに何ができるか、真剣に考え取り組むときがやってきたようです。そのためには、一人一人の子どもの個性を見とり、何を望みどう育っていきたいかを察知し、子ども自身がそれを生かしていけるような仕組みをつくり出せる「私たち自身」になること、それが求められていると言って良いのかも知れませんね。
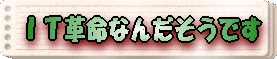
森総理のこのところの口癖は「IT革命」。いつぞやは、秋葉原まで出かけて行って、パソコンの売り場を視察してきたとか。また、「森メール」の発信をめざして、パソコンの講習(しかもマン・ツー・マン)を受けていたのに、ひどく肩が凝ってしまい、たった3回で挫折しちゃった模様。それでも相変わらず「IT革命」を言い続け、コンピュータを教わる際の補助としての「IT講習券」のばらまき構想まで言い出す始末。
ご存知のように「IT」は「Infomation Technology」の略です。文字通り「情報技術」の意味ですが、総理は「情報」やその「情報を生産・発信・受信・操作すること」をコンピュータを「使うこと」と勘違いしているのかも知れません。
私たち人間は、太古の昔からその時々に応じてさまざまに情報を生み出し、伝え、やりとりしてきました。狩猟が生活の中心だった時代ですら「山のむこうにイノシシがいたぞ」とか「うまそうな実がなっているぞ」「昔これ食べた○○死んだ。今おまえ同じもの食べた。おまえ顔色わるい。おまえ死ぬ。おれ食べない。これおれたち殺す草。」などと情報を生産し、伝え、受け取り、生活に役立てていたはずです。
現在のように続々と大量の情報が生み出される状況とは違うとは言え、そして扱う情報が「音やことば」と「石や紙に書かれた文字」によるアナログなものだけだったとは言え、コンピュータが出現する前までは、さまざまな問題を頭脳に置き換え、思考によって様々な問題を処理し解決してきたはずです。
問題を分析し論理的に整理し直し、組み立てながら問題を解くといった過程を人間の頭脳だけで行ってきたのです。
その過程は、「分析」と「統合」の活動と言って良いでしょう。中味を調べ、組み立てる活動だからです。
そこで要求されるのは、分析力、論理力、判断力、設計能力などと呼ばれるものでしょうが、対象を情報に限れば、情報活用能力(情報リテラシー)と考えて良いでしょう。
情報活用能力は、情報を対象にしていて、人間の脳で処理するのですから、情報の入力は「収集」、情報の処理は「蓄積、判断、整理」などで、出力は「伝達、創造」ということになるでしょう。
そのような情報の活用や処理を人間の頭脳だけで行ってきたのですが、情報を速やかに大量に確実にそして迅速に処理するためにコンピュータの導入が有効だったというのが、どうやら私たちの今いる現実世界であると言えそうです。
ですから、情報を処理(操作)したり生み出したりする能力や構えは、もともと人間に備わったものだと言えそうですし、基本的にはコンピュータを「使える」こととは別物だとも言えそうです。
別な言い方をすれば、情報を処理・活用する能力(情報リテラシー)はコンピュータを使うかどうかにかかわりがなく、コンピュータが役立つかどうかはコンピュータを使う人がそれを使って「何をするか、何をしたいか」にかかっているとも言えそうです。
もっとも、現在のようにどこからでも情報を受け取り、どこへでも情報を伝えられるインターネットという世界共通の基盤が出現したのはコンピュータがあったからこそだ、ということが言えそうですが、それだって今やコンピュータなしで出来てしまうのです。
情報端末がコンピュータから手のひらに乗るような小さな電子手帳へ、さらに携帯電話
がその機能を併せ持つというように、パソコンなど使わなくても情報を収集・活用できる時代になってきて、ますます「パソコンを使えること」と「情報リテラシー」の間の隔たりは広がっていきそうです。
大手の家電メーカーでは、たとえば電子レンジにインターネットへの接続機能を組み込み、つくりたい料理を選択すると自動的にインターネットからレシピの情報を引き出し、それに沿って自動調理をしてしまうようなものの生産も目論んでいるそうです。
そうなると、ことさらに「インターネットを活用している」という意識を持たずにインターネット上の情報を活用できてしまう(それもごく普通の家庭の普通の主婦が)という状況が出現することになります。
情報端末は、コンピュータ(パソコン)に限らないし、これからますますその傾向は強まっていくことが予想されます。
デジタルデバイド(デジタル機器を使える人と使えない人の格差の問題)がとやかく言われていて、とにかく小さな頃からそれらの機器に触れさせ、使いこなす力を身につけさせておくことが大切だという主張をする人も大勢いるようです。
しかし、上のように考えてみると、機器を「使えるかどうか」ではなく、その機器を使って「何をするか」「何がしたいか」を持っているかどうかの方が重要な問題だと言えそうです。
もちろん、何か「したいこと」があっても、機器を使いこなすことができなければ何も始まらないとも言えます。しかし、それらを「使う力」は後でいくらでも身につけることができますが、「したい何か」を持つことや情報を「操作・生産・発信する力や構え」は、そうはいかないと思われるからです。
その証拠に、私たちが子どもの頃にはコンピュータなど生まれておらず、大人になってからそれらの機器に出会ったにもかかわらず結構使いこなせているではありませんか。
大事なことは、まず知りたいことがあること、そしてそのために情報を収集・選択出来ること、そして集めた情報を組織し直して新しい知識を創り上げること、友達と共有したり他の誰かに伝えられることなどではないでしょうか。
機器に出会って『これは便利だ。これは使える。使ってみたい。』と思えるのは、そうした資質や期待があるからこそで、まずそれを子どもたちにわかってもらうこと、培っていくことが大切なのではないか、と思われてなりませんがいかがでしょうか。
昨晩、私のパソコンの中のテキストフォルダを何気なく眺めていたら、昨年の朝日新聞「天声人語」を写し取ったテキストファイルが目に止まりました。
興味深い内容だったので、保存しておこうと思って写し取ったものですが、それきり忘れていたもののようです。ご紹介しますので、ご一読下さい。
***************************************************************************
お年寄りと一緒に作曲 作曲家の野村誠さん(天声人語)
1999.06.06 東京朝刊 1頁 1総 (全747字)
食堂のテーブルに、さまざまな楽器が並べられた。カスタネット、ハンドベル、
トライアングル、太鼓、マラカス、おもちゃの鉄琴。けん玉やアルミの食器まで
ある▼
十人ほどのお年寄りが集まってきた。若い作曲家、野村誠さんは、この半年、
横浜市の特別養護老人ホーム「さくら苑」に通って、お年寄りと一緒に作曲に取
り組んでいる。ホームの愛唱歌「わいわい共和国のんきぶし」ができあがりつつ
あるところだ▼
歌詞は、前回からのつづき。「にこやかに」がいいね。「ほがらかに」がいいよ。
両方入れよう。こんな具合に作詞がすすむ。メロディーも同じやり方だ。気に入
った楽器をてんでに吹いたり、たたいたり、こすったりしながら、だれかが口ず
さんだ一節をみんなで吟味してつなぐ▼
作曲途上の曲は民謡のようでもあり、ラップのようでもある。野村さんはプロ
の作曲家なのに指示も指導もしない。「あ、すごくいいな」「次、どうしましょう
か」などと、時折、口をはさむだけだ▼
「さくら苑」では、心身の活性化のためにいくつものグループ活動をしている。
「そのなかで、このグループの仲間がきわだって生き生きしている」
と苑長、桜井里二さんは不思議がる。一人ひとりの力が引き出される。ぼけ防止
や健康維持などの手段としてではなく、音楽そのものを楽しんでいるからでもあ
ろう▼
野村さんは、留学先のイギリスやインドネシア、日本の各地で子どもたちとの
作曲や演奏を重ねてきた。譜面に頼らずほかの人が出す音を聴きながら自分も音
を出す。そういう演奏では脱線や創造的なまちがいが次々に起こる。それにわく
わくさせられる▼
一方が作品を送り出し、一方は鑑賞する。芸術家と市民のそんな関係を、創造を
対等に楽しむ関係へと変えていきたい。
野村さんの小さな試みには、実は大きな野望が秘められている。
**************************************************************************
いかがでしょうか。
この短い文章は、私たちが学校教育を考える、あるいは見直す上で多くの示唆を与えてくれているとお思いになりませんか。
まず、野村さんが『プロの作曲家なのに指示も指導もしない』ということ。
そして一方では、『あ、すごくいいな』『次、どうしましょうか』とお年寄りからアイディアを引き出しつつそれをしっかり受け止めうなずいていること。
何よりも、この活動がお年寄りの「ぼけ防止」や「健康維持」などのためのものではなく、活動そのものを(ここでは音楽すること、創作すること)楽しんでいること。
自分の感覚を敏感に働かせる活動の中で起きる『脱線や創造的なまちがい』をわくわくしながらみんなが楽しみ、それがいっそう老人の『きわだったいきいき』とした姿につながっているらしいこと。
さらに、作曲家と演奏家、そして聴衆の関係を『対等に楽しむ関係』としてとらえなおすことを暗黙裡に提案していること。従来、演奏家の多くは、作曲家の意図を楽譜から汲み取り、それを忠実に演奏し聴衆に伝えることを使命としてきました。最も偉い作曲者の創作意図を具体的な演奏の姿に変えて聴衆に伝え、楽しませるのが次に偉い表現者としての演奏家であり、聴衆は単なる享受者として最も低い位置にあるという構図が見え隠れしていたのです。それはまったくの誤解なのですが、そのように思い違いをしている作曲家や演奏家が多い中、この野村さんの活動はプロの作曲家としては注目に値します。
閑話休題、私には、野村さんの活動には通奏低音のように『送り伝える者のおごりとは無縁の真の奉仕』の心が一貫して流れているのではないかと思われるのです。(これがこの稿の主題なのですが・・・・)
「あなたのためにしてあげている」という行為は、音楽活動の主体者である老人たちに何の喜びも楽しみももたらさないでしょう。野村さんの活動が老人たちのいきいきした創造につながっているのは、野村さん自身が老人と同じ視点で「つくったり表現したりできること」に喜びを感じ楽しさを味わっていることによるのではないでしょうか。
ひょっとすると野村さんは老人たちのそんな姿に接して嬉しいしのかも知れませんし、
もっと想像を広げて良いのであれば「老人たちのそんな姿から新しいパワーをもらっている」のかも知れません。ですから野村さんは、「老人たちのためにしている」のではなく、他ならない「自分自身のため」「自分自身の喜びのため」にしているのかも知れません。
そして、私はそれが本当の「奉仕」であって、そうでなければ「偽善」としか呼べないのではないかとも思っています。
総合的な学習では『ボランティアの活動がしたい』と思っている子がいるかも知れませんし、多くの識者もそれを進めていますが、偽善的な奉仕活動にならないようにするために、これから何を育んでいくか考え吟味する必要があるのではないでしょうか。
長宗我部元親と言えば、岡豊という土佐の片田舎から身を起こし、半生の間にほぼ四国全土を切り従えた勇猛な武将として有名ですが、高校の日本史の時間でも「長宗我部元親百箇条」について習いましたし、テストにもよく出題されましたので、私たちにはおなじみの殿様です。
その元親の長男(幼名千扇丸、後の信親)は非常に臆病だったそうです。5才になって初陣に出る折にも怖じ気を感じているのを見て取った元親は、意外にも大変喜んだと言われています。
勇ましく戦陣を駆けることこそ喜ばれるはずの武士の家庭で、なぜ元親が「それは頼もしい、将来を託せる子だ。」と喜んだのかというのが今回の話柄です。
元親は言います。『自分は生来の臆病者だ。幼い頃から姫若子と呼ばれていたほどだ。それゆえ、昔から合戦がこわい。』しかし、『臆病者こそ智者の証拠であり、臆病こそ智恵のもとであるし、智恵のある者でなければ臆病にはならない。』『そのことは自分自身が人一倍臆病であるからよくわかる。』
さらに続けて、『幼い頃に物の影や音をさまざまに想像して恐れたが、それは想像力を豊かすぎるほどに持っているからで、逆に豪胆なのは鈍感の証拠であり無智の証拠だ。』と言ったと言われています。
想像力が豊かだからこそ臆病心も生まれるし、その心配事にうまく対処するためにさまざまに智恵を働かせ、あらゆる手を尽くしてその懸念を克服していったり、自分自身を練って自らを鼓舞し勇気を獲得したりしていくのだ、ということなのでしょう。
だから、自分の跡を継ぐべき嫡子が臆病であることを非常に喜んだというのです。
彼はそのように智恵を働かせ、工夫を凝らした戦法を用いて近隣諸郷を切り従え、ゆくゆくは四国全土のほとんどを制圧することになるのですが、その陰にはこのような周到な準備につながる恐怖心や臆病心があったということに私たちは着目してよいでしょう。
元親がもう一歩で四国全土を制圧しようかという時に、それを阻んだのは尾張のほとんど浮浪児と呼んでよいような境遇から身を起こし、考えられないような立身をして織田家の有力な将になっていた羽柴秀吉です。
その秀吉も同じような感覚の持ち主だったようで、彼は実際に槍や弓をとって戦うことよりも「調略(計略、策略)」にその本分を発揮したと言われています。
武器をとって戦うに足る頑強で大きな体と膂力があればそうはならなかったのでしょうが、幸い秀吉は貧弱な体しか持っていなかったために「工夫を凝らし智恵を働かせる」ことに長けていったのだろうと見ることもできるでしょう。
戦を始めるずっと以前から、敵方の武将に働きかけ、時には内応させ時には敵を分裂に追い込み、実際に戦いが始まる時にはまるで熟した柿が自然にぽとりと地面に落ちるように勝利が手に入るだけの下準備にあらゆる手を尽くしておいたと言われてます。
そのように想像力を存分に働かせ、予想できる限りのあらゆる状況を思い描き、創造力を働かせて策をめぐらし、どう転んでも勝てるだけの手を打っておいて、ようやく戦いを始めたというのはよく知られた話です。
その場その場の状況に応じて瞬時に対応策を打ち出し、エイヤッと一発勝負をかけるようにして成功を得られるのはほんの一握りの天才だからこそできることですが、前もってさまざまに状況を予想し、地道に対処の手を打っておくことは私たち凡人にもできそうですし、むしろその方が確かな実践につながっていくのではないかと思われます。そればかりではなく、私たち自身の財産としての貴重な糧になるとも思われます。
『失敗を恐れるな』とよく言われますが、何の手だてもなくそれゆえ何の裏付けや根拠もなくただ単に「恐れない」のだとすれば、それは「蛮勇」でしかないでしょう。
「失敗を恐れる」からこそ失敗を回避するための智恵を働かせようとするし、そうできてはじめて「失敗を恐れない」確かな安心を得ることができたり、成功を得る確率を高くすることができるはずです。
翻って、私たちの日々の授業に臨む姿勢はいかがでしょうか。
私が若い頃には、よく先輩の先生から『教壇で勝負しろ』とよく言われました。
しかし私はある時期から、そうではないだろうと思うようになりました。
元親や秀吉の例に見るように、勝負は「教壇に立つ」前に決めておくべきだと思うようになったからです。(もっとも先輩諸氏の指摘は、教壇に立った時だけに勝負をせよ!というような浅薄なものではないとは思いますが・・・)
その日その時間の授業が成功する、つまり子どもたちがよりよく学べるような授業を展開するためには、教壇に立つ前にさまざまに工夫を凝らし吟味し、学習が始まった時にはほとんど手を下さなくても学習が成立するだけの「臆病なほどの心配」をすることが肝要なはずだとの思いに実践を通して至ったからです。
初発の資料はこれでよいか、初発の発問はこれでよいか、それともこう言い換えた方が課題をよりよく把握できるだろうか、この言い方で一時間の活動の見通しが持てるだろうか、やってみようという意欲が持てるだろうか、やる意味を感じることができるだろうか、資料の提示は印刷物でしようか、それともOHPで視覚に訴えようか、板書の構成はこれでよいか等々、子どもの目で自分のしようとしていることを吟味し、失敗を恐れて心配しながらあの手この手を考えることが私たちの財産にもなっていくし、子どもたちに「学習をあずける」ことが望まれるこれからの授業づくりの上で大いに役立つはずです。
しかし、悲しいことに人間は経験を積むほどに「小手先のワザ」が身に付いてしまい、それで事足れりとする満足に安住してしまいがちです。目の前の子どもは以前に受け持った子どもとは違うのに、前にうまくいったからという理由だけで「だから今度もうまくいくはずだ」「うまくいかないのは子どもの努力が足りないせいだ」という慢心に似た妙な安心を背景に一発勝負の授業に臨んでしまったことも一度や二度ではありませんでした。 元親も秀吉も相手の人柄や好み、長所や欲するところをよく見据えてとらえ、相手に応じて策を練って変えた結果が勝利につながったはずで、一度の成功に気をよくし同じ手をいつでも使うということはなかったはずです。
臆病だから細心の手はずを整えることができ、それがあるからこそ大胆でダイナミックな展開をすることができるのではないかと私は常々考えています。
さて、明日の授業にはどんな用意周到な準備を整えておきましょうか。
一昨日のことです。
どうしたはずみでか、購入して間もないiモードの携帯電話を水たまりに落としてしまいました。水没した電子機器を生き返らせる術はなく、新しい携帯電話を買わなければならない羽目に陥ってしまいました。それだけでもがっかりなのに、水没させてしまった携帯電話に蓄積したデータもすべて諦めざるを得なくなってしまい、落胆を絵に描いたような(そんな喩えはないか)気分に陥っています。
その晩、長女にメールでそのことを知らせたところ、早速返事が返ってきました。
曰く、『あらら、でも新世紀を新しい携帯で迎えられると思えば!!!(^-^)』
そうですね。何事もプラス思考でとらえて明るくいきましょう。
という訳で、携帯電話にまつわる話題で、2000年を締めくくりたいと思います。
iモードは、NTTドコモが設けた携帯電話向けのインターネット接続サービスですが、これが出たおかげでその後他の携帯電話の会社も続々とインターネットに接続できるサービスを開始する魁となったものです。
ところで、このiモードの生みの親は、松永真理さんという女性で、その活躍が認められ2000年「アジア・ビジネス界最強の女性」に選ばれた方です。
松永さんによれば、それまでコンピュータともインターネットとも無縁だったそうですが、それが却って幸いしたとか。無縁だったからこそ、自分のような女性でも子どもでも、誰もが予備知識なしにインターネットを使えるような機器が欲しいと思い、その実現に向けて技術屋さんに無理難題を吹きかけ、とうとうiモードを世に出すことができたと言うのです。
その松永さんが、受賞を聞いて語った喜びの言葉は、『成功する、しないより、新しいことに取り組むプロセスが好き』(I like the process of working in new things rather than caring about if what I do will be successful or not )だったそうです。
松永さんは、その言葉通り、iモードを成功させてしまうと今年ドコモを退社してしまい、現在は女性のためのホームページ「eWoman」開設に参加し、その編集長をされているそうです。新しいことに取り組むために、成功の場をさっさと離れてしまうというのは、何とも小気味のよい松永さんの人柄と生き方が偲ばれるようなエピソードです。
自分の可能性を信じて仕事をどんどん変えるということは別にして、新しい事への取り組みのプロセスを楽しみ味わうということは、人間としてこれ以上の楽しみはないのではないでしょうか。
成功や失敗というのは、あくまでも結果なのですが、どうも成功を目標にしてそれが得られないと何の成果も得られないのだとする気分にとらわれがちなのは凡人の悲しさでしょうか。誰かも言ったように『成功からは何も学べないが、失敗からは多くのことが学べる』はずなのですが・・・。
ですから、子どもたちには新しいことにトライしチャレンジすることそのもののおもしろさをどんどん楽しもうよ、という呼びかけをしていきたいのです。
かの孔子も
これを知る者は、これを好む者にしかず
これを好む者は、これを楽しむ者にしかず
と言っているではありませんか。
ある何かに挑戦し取り組むことを楽しむことは、研究の基本的な姿でもあります。
ノーベル賞を受賞された白川英樹先生のお話からもそのことが窺えます。
翻って「総合的な学習の時間」は、子どもが子どもなりの取り組みで「研究」ができ、まとめあげる中で、「学ぶ力」や「学び方」、そして「学ぶことの味わい」を感得していけるような時間として設けられたものです。
自分の持てる力の精一杯を発揮してものごとにぶつかっている「いま」が楽しい、と思えるようなチャレンジャーとして子ども自身が自分を意識できることこそ肝要なのではないでしょうか。
何と言っても21世紀です。
19世紀の人々は20世紀を「輝かしい明るい未来」と見ていたでしょう。21世紀はそのときほど明るい夢に満ちているようには思えませんが、だからこそ余計に気持ちを奮い立たせて「答えの見えないトンネルの出口」を見出せるような人間の育ちに貢献できるような学校や社会にしていかなければならないのではないでしょうか。
そこでオープンエンドな問いに対して、新しい考えや方策を打ち出しさまざまな角度から検討しよりよい解を見いだせるような力や粘り強く取り組む構えをこそ育てていくことが求められているのです。
元気を出して21世紀を迎えようではありませんか。
閑話休題、先頃「創作四字熟語」というホームページを見つけました。
中でも秀逸なのが
圏外孤独 (天涯孤独のもじり)
何だかおかしいでしょう?思わず「うまい!」と声をかけたくなりますね。
携帯電話でしょっちゅう、というよりのべつ幕なしに不特定多数の友達と携帯電話で話をしている高校生などを皮肉ったものでしょうが、圏外になって電話がかけられなかったりかかってこなかったりすると途端に寂しくなってしまう、という姿は想像しただけでも滑稽だし、それでいいの?という思いにもかられます。
困った事件や暗い話題、これまでに人間が出会ったことのない奇異な現象が浮き彫りになった世紀の終末ですが、21世紀はよい世紀でありますように。

学習意欲にまつわる問題は、私のこれまでの教員生活における最大の関心事です。
ここで言う「学習への意欲(=やる気)」は、『いっちょやったるか』というときのような一過性の「やる気」ではもとよりなく、まして『宿題があるからしっかりやろう』といった他発的なそれでもありません。それは、自分にとって学びがいのあること、捨ててはおけないことの解決に向けて「粘り強く問い続ける行為」を支えるところの、自律的で、苦しいかも知れないが悦びに満ちた、無我夢中になれるときの「やる気」です。
言葉を換えれば「フローの状態」のときに見られる「内発的な意欲」のことです。
誰にでも覚えのあることでしょうが、傍からみれば「汗水流してずいぶんがんばるなあ」と思われることでも、本人はそのことに熱中するあまり「難行苦行」しているという実感なしに時間の経つのも忘れて打ち込んでしまう、ということがよくあります。
それがテレビゲームであれ、サッカーであれ、お菓子づくりであれ、読書であれ、私たちはほんの小さな子どもだった頃からそういう経験を幾度となくしてきたはずです。
父や母から『もう遅い時間なのにいつまで遊んでいるのか』と叱責をくらっても、もうその翌日はそんなことはケロっと忘れて、時間の経つのも忘れてしまうということがよくあったことを思い出します。なぜそんなに夢中になれたかと言えば、それらの行為(遊びでも運動でも)の中には、何かしら解決しなければ気が済まない課題、乗り越えてみたいと思わせる障碍が横たわっていたように思われます。『今度はもっと遠くへボールを飛ばしてみよう』とか『手放しで自転車に乗れたらどんなに楽しいだろう』といった具合に、もっとうまくやるためのさまざまな試行錯誤を繰り返し、ときにはくじけることがあっても「なにくそ」を発揮してどんなに多くのことを身につけて来れたことでしょうか。
もしかすると、それらは「教えてもらって覚えたこと」よりも質・量ともに自分にとってずっと意味のある「生きて働く力」になっているかも知れないとも思えるのです。
それらは「こうなってみたい」という憧れに満ちた対象だったということもあるでしょうが、そう考えてみると、どうやらそのように夢中になれる意欲の底には「対象の持つよさ」に気づいてしまったこと、しかも楽しさや悦び、つまり「快の感情」を予感させるようなものであったことが大きな要因としてあるように思われてなりません。
私は、これまで人間が意欲を持続させて問い続けられるのは、ある目標に向かって目的的に取り組めるような内容だと思えるものだからだ、と事あるごとに言い続けてきました。
たとえば、お料理をするにしても、もしそれを食べてもらいたい相手、そして『おいしい』と言ってもらえる相手がいるとしたら、お料理にもハリが出るでしょう。
その相手はどんな味が好きか、どんな食材を好むか、どんな調理法なら満足してもらえるかなどについて、さまざまに吟味し、『おいしい』と言ってもらえるかどうかドキドキしながら調理に取り組むことでしょう。
しかもそのあいだ中、相手を意識し、その相手に満足してもらえるかどうか、いま作っている料理を常に自己評価しながらがんばってしまうのではないでしょうか。
そのようなとき、調理それ自体は目的として意識されていないはずです。
目的は、「相手においしく食べてもらうこと」で、調理はその手段。
しかし、そこでは確実に調理の意味を実感したり、調理の腕を上げたり、調理そのものの楽しさを味わったり、あるいは食材の扱い方や調味料の使い方などを「つくる実体験」を通して身につけたりしていけるだろうと思われます。
さらにそのような状況では、調理の工夫をすることが他から指示されたり、「やらねばならないこと」として意識されたりしているわけではありませんから、その人の内から生まれた「内発的な意欲(あるいは内発的な動機)」だと言うことができるでしょう。
良いことづくめのそのような状況を創出できるのは、それがある目標に向かう行為(ここでは「相手においしく食べてもらうこと」をめざした行為)を促す環境だからだ、と言えますが、私はそれを「ステージへのモード」と名付けました。
その必要性を長い間主張し続けてきましたが、一方では先に述べたような「それ自体が楽しい」ので夢中でしてしまう、という「場のモード」もあるとも思い続けてきました。
「試合」というステージで勝つために練習するのではなく、ボールを追いかけることそれ自体が楽しい、シュートの練習がおもしろくて飽きずにそれを繰り返してしまう、などのことが結果として「力や技」を伸ばすことにつながることもよくあるからです。
ですから迷い続けて来たのです。私たちが学習を仕組むときにどちらのモードを備えた環境を子どもたちに提供すれば、より自然な学習ができ、子ども自身がやる気を発揮して学習の効果を上げることができるのか、ということについて。
どちらも「内発的な動機」を支えに学習を展開していけることをめざしていますが、それは「教わって習う」ことから「自ら学び取る」ことが求められるこれからの学校教育を考える上で避けて通ることはできないことです。
殊に、個々の子どもの主体的な学びを保障し、内発的な意欲に支えられた「問い続ける姿」をめざす総合的な学習を構想する上で、それはとても重要な課題となるはずです。
残された字数が少なくなってきました。未だ判然と構造化して説明できるまでには至っていませんが、多少結論めいた言い方をするとすれば、この2つのモードはどちらも「問い」を発して粘り強く取り組む上で、不可欠なのではないかと思い始めているのです。
「問い」は、単なる疑問なのではなく、モノゴトに対する「驚きや感動」「よさや不思議さの実感」などであり、だからこそ『何とかしたい』という「問い」が生じるのです。
そのためには、「場のモード」でたっぷりとモノゴトに浸り、触れる体験を欠かすことができませんし、そこで生まれた「問い」を柱に「ステージへのモード」に触発されることで、「問いの解決」に向けた活動にますますはずみがつき深まりを求めて動き出すのだろうと思われるからです。おそらく、「ステージへのモード」の中で活動しているときにも、「解決に向けて夢中で取り組む」といった具合に「場のモード」が機能することも考えられます。誤解を恐れずに言えば、両者は互いに影響を及ぼし合い、人を学びに駆り立てていくのかも知れません。
そこで、本当にその子なりの「問い(こんなことをしてみたいという衝動も含めて)」を生ましめたいのであれば、まず「場のモード」を創出できるような手だてを、さらにその「問い」の解決に向けて自発的な取り組みを期待するのであれば「ステージへのモード」を備えた環境を設定することが有効なのではないかと思われるのですが如何でしょうか。
明治時代に入って全国に学校を設置する動きが起き、井澤修二が音楽取調掛の中核となって西洋音楽の学校教育への導入に奔走し、それ以降100年以上の長きにわたる学校音楽教育の伝統をつくりあげたことは、音楽科を担当する者にとっては周知の事柄です。
井澤は、音楽を学校に普及させるに及んで次の三原則を打ち出したと言われています。
1 西洋音楽をベースにした教材曲を生み出すこと
2 音楽の教員を多く輩出すること
3 学校に音楽教育のシステムをつくりあげること
第一の項目によって、600曲を越える「文部省唱歌」が創出され、全国どこの学校を出ても、誰もが歌える曲として定着し、100年以上経た現在でも小学校や中学校で扱われていることを考えると驚嘆に値します。
こんなに全国にわたってシステマティックに、そして多くの人間に音楽を学ぶ機会を与え続けた国は他に見あたらないでしょう。同じ曲をすべての学校で習い、「おぼろ月夜」を「ふるさと」をおじいちゃんから子どもまで、世代を越えて一緒に歌うことができる国など、どこにもないからです。
かつてのラジオもテレビも、もちろんレコードなどもなかった時代、もう退官されたある大学の先生などは子どもの頃、何ヶ月かに一度、担任の先生が町で受けてくる講習会から帰ってこられるのを大変楽しみにしていたそうです。新しい歌を仕入れてこられた先生から、それを口伝えに教えてもらうのを首を長くして心待ちにしていたというのです。
想像するに、それは渇いた土に水がしみこむような楽しい時間だったはずです。
まさに学校と先生は「新しい文化の担い手・発信者」だったのでしょう。
それはそれでよかったのでしょうが、いつの間にか「文部省唱歌」を教える時間が音楽の時間になってしまい、呼び名も「唱歌の時間」と呼びならわされるようになってしまったようです。つまり、「教材曲を教える」ことが教師の主な務めであるとされ、その伝統を今も引きずっているように思われるのです。
音楽科の目標は、本来ある楽曲が歌えるようになること、あるいは演奏できるようになることなのではなく、その楽曲に触れることによって「音楽のよさ」を味わったり、音楽に働きかける行為を通して表現することの喜びや楽しさを実感し、ひいては心の豊かさや生きる上での自信や勇気を獲得することにこそ意味があるはずです。
ところが教材を教えることを主な目的としてしまってからは、何よりもまずその楽曲を正しく歌うこと、上手に歌う(演奏する)ことへの指導に重点が傾いてしまい、教師はそれらを指導するために「どうすればよいか」「どうしたらうまく指導できるか」のみに心を奪われるようになったかに思われます。いわゆる「指導法の研究」への傾斜です。
教える内容が規定されてしまえば、勢いそれらを「どう教えるか」に関心が集中することは避けられないでしょうが、明治以来、教師は常に「指導法の研究」にその労力の大半を費やさなければならなかったのも、おそらくそのような経緯によるのでしょう。
そのような「教材中心主義」を背景にした「指導法への傾斜」は、ひとり音楽科だけではなく他の教科にも通じる問題なのではないでしょうか。
指導の「方法」ではなく、子どものどのような育ちをめざすか、そのために教科ではどんなことについて学ぶことのが望ましいかといった内容や価値に目が向けられるようになったのは、ほんの20年ほど前からで、私もことあるごとに「方法論から価値論(内容論)への転換」を指摘してきましたが、依然として方法論(教え方の工夫)から脱却できずにいる現状も見受けられます。新しい学力観の論議にも見られるように、これからの教育では、どんな力や構え・資質を育むかといったことについて上意下達の形でではなく、それぞれの学校や教師が見極めて教育活動に臨むことが求められています。すなわち、「価値(内容)」について論じ、考え、見定めていくことが私たちの教育活動にとって不可欠かつ重要なことで、そこに私たちが「専門職」として拠って立つ場があると思われるのです。
そんなことを考えていた折、次のような論文の出会いましたので、ご紹介します。
*****************************************************************************
「学校再構築に向けての基本原理」
教育展望2001、1+2月号
p25..26
越智康詞信州大教授
~ 略 ~
ひとつは、教師の教育観や人間観の転換である。専門職の視点に立つと、教師は社会で自信をもって自由に生きる力=実践力を保障するという公教育の理念を、現実の教育実践により自覚的に結びつけて考えるようになり、そうした力を損なう組織的構造や集団的圧力に対して敏感になるだろう。これまでの学校がそうであつたように「(組織的統制にとっての)都合のよさ」を求めるあまり、何事に対しても無批判で主体性のない「指示待ち人間」を大量生産することは、もはやありえないこととなる。
あるいは、学級活動における「望ましい集団づくり」の「望ましさ」の意味転換も生じるだろう。つまり、「秩序=集団のまとまり」を重視する集団づくりから、差別を許さない、子どもたちが安心して生活できる安全な空間づくり、ひとりひとりが自己の意見を持ち、表現し、相互交流を促すような民主的な学級づくりへと、その実践の方向は転換するであろう。
さらに、専門職教師は、カリキュラムの伝達者から子どもの学びの責任者(アドバイザー)へとその役割が転換することに応じて、現状への批判にとどまらず、新たな実践領域の開拓、そして、そのための環境づくりにも積極的に関与するようになるだろう。
本来、学びとは、知識の所有や思考能力の向上に限定されるものではない。学ぶ行為は、「心が世界に対して開かれてあること」「世界にかかわりを持つこと」と不可分に結びついており、何か学びがいのあることを学び、その悦びを味わう場や機会を提供することは、民主主義の理念の実質化を目指すプロジェクトにおいては不可欠の条件なのである。このように考えると、専門職としての教師は、「学校に背を向ける」子どもたちを、実践を困難にする困った状態として嘆く(切り捨てる)ことはなくなるだろう。むしろ彼らは、子どもたちを「関係ない=わからない(ど-せダメ)」という世界疎外・自己否定への悪循環から救い出し、「興味・関心=関与・探求=わかる・楽しい=新たな関心・問題意識」といった意味や関係の編みなおしの循環に導くことを、その職責=誇りと感じることになるだろう。
******************************************************************************
教え方を工夫し、名人芸を身につけるのは町の学習塾の講師でもできます。
専門職としての私たちにしかできないこと、私たちにこそできることは何か、ということについて見直しとらえ直していくこと、それは言い換えれば「教育を哲学すること」だと言うことができるでしょうが、それがすべてのベースになることを銘記したいものです。
「総合的な学習の時間」を試行する中で、このところ多く目にするようになったのが、「ワークショップ」という活動形態です。そこでここでは、なぜ「総合的な学習の時間」に「ワークショップ」がなじむのかということを考えてみたいと思います。
「ワークショップ」とは、もともと「共同作業場」や「工房」を意味する英語ですが、ここ十数年の間に多少概念が変わってきて、現在は「先生や講師から一方的に話を聞くのではなく、参加者が主体的に論議に参加したり、言葉だけでなくからだやこころを使って体験したり、相互に刺激し合い学び合う、グループによる学びの創造と方法」という意味で使われるようになったようです。
広辞苑には次のように記されています。
『②所定の課題についての事前研究の結果を持ち寄って、討議を重ねる形の研修会。
教員・社会教育指導者の研修や企業教育に採用されることが多い』
やはり一方的に聴講するだけでなく、参加者が持ち寄ったり討議を重ねたりする「参加型の研修の場」という意味でとらえていることがわかります。
学校での学習に限らず、新聞の催し事案内でも「ワークショップ」と名付けられたイベントがあちこちで行われています。
試みにインターネットでキーワード検索をしてみました。ヒットした数は次の通りです。
Yahooで検索したところ「164件」
Lycosで検索したところ「40,425件」
excite での検索では「48,503件」
gooに至っては「75,647件」もヒットしました。
これらは、ホームページで公開されているものだけです。
ひょっとすると「ワークショップ」と銘打ってはいないけれども、実質的にはワークショップ的な内容や方法による体験学習や参加型の企画、ホームページで公開されていないものも含めたら探したら数え切れないほどになるのではないでしょうか。
私たちはさまざまな問題を抱えた社会(世界)に暮らしています。
環境汚染、教育、社会不安、人権、平和、経済不況、人口問題、少子化問題等々、現在の私たちが抱えている問題はどれをとっても複雑に広く絡み合っていて、単一の原因に因るものではなく、それだけに容易に解決の糸口が見出せそうもなく、明快な唯一の解決策もなさそうです。
そう考えてみると、おそらくこれらの問題に対して「一つの正解」や「確かな解決への道」を示せる専門家などいないのではないかとも思われます。そんな時代だからこそ、私たち一人一人があきらめたり孤立したりしないで集い合い、問い合うことが大切になるはずですし、それぞれが智恵を出し合いよりよいと思われる方向を模索することで解決をめざすことが必要になると思われるのです。
だからこそお互いに学び合ったり創り出したりする「学びと創造のスタイル」としての「ワークショップ」があちこちで展開されているのでしょう。
「ワークショップ」は、「参加体験型グループ学習」などと訳されることもあります。
ここまでに見てきたように「ワークショップ」は「参加と体験、グループ」の3つがキーワードになる学習法です。
「参加」は、先生や講師の話を一方的に聞くのではなく、自ら主体的にかかわっていくこと。「体験」は、頭脳だけではなくからだとこころを丸ごと総動員して感じていくこと。「グループ」は、お互いの相互作用や多様性の中で分かち合い刺激し合って学んでいく双方向性を示しています。
さて、「体験」についてですが、ある研究者※は「体験学習法」について次のように述べています。
体験学習法とは何らかの体験をすれば、そのことだけで、学習した
とするものではない。
今、ここでの体験によっての気づきにこだわり、さらには、ともに
体験して、気づいたこと、感じたことをわかちあい、その解釈から、
学びを深めて、次の行動へと生かしていく循環過程として、構造化
される教育方法のことをさすのである。
さらに、「体験学習法の循環過程」として次の4つのステップを説明しています。
①体験する(やってみる) ②指摘する(観てみる) ③分析する(考えてみる)
④概念化する(まとめる、次を考える)
そして、この②③④の段階は、「ふりかえり」と呼ばれる大事な部分で、経験共有者の「わかちあい」によっても効果が高まると言うのです。
ワークショップでも、①いろいろな体験をしたあとに、②まず個人でふりかえり、③それを他の人とわかちあい、④さらに自由に話し合う中で学びを深めていく、という構成をとることが多いようです。
これは、そのまま「総合的な学習」での学び合いの姿ではないでしょうか。
体験を通して事実に基づいて学ぶことが求められる総合的な学習、問い続け学び合う姿をめざす総合的な学習に、ワークショップはまさにうってつけ。これからもますますこのスタイルを採用してその効果を確かめたいと思うのですが、そのためには単なる発表会のようなものにしてしまわずに、全員が主体的な参加者として「一緒に考え、悩み、解決を模索する」ことができるようなワークショップにしていけばよいのではないでしょうか。
最後にワークショップの要点を列挙します。
*********************************************
○ 先生はいない
○「お客さん」でいることはできない
○ はじめから決まった答えなどない
○ 頭が動き、身体も動く
*********************************************